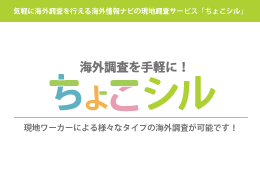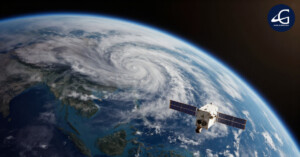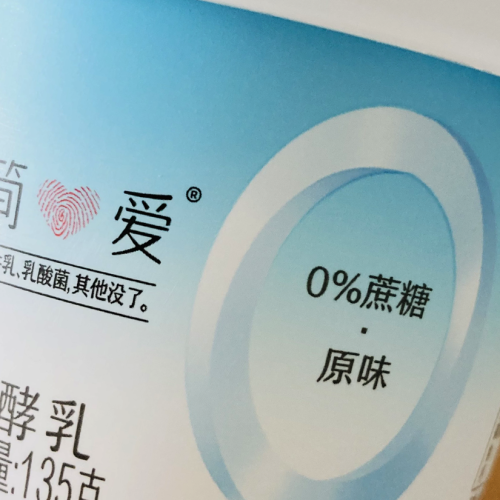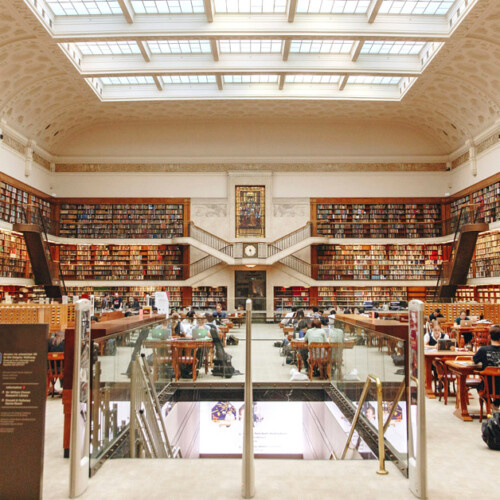マレーシアの独立記念日に見る祝賀の変容
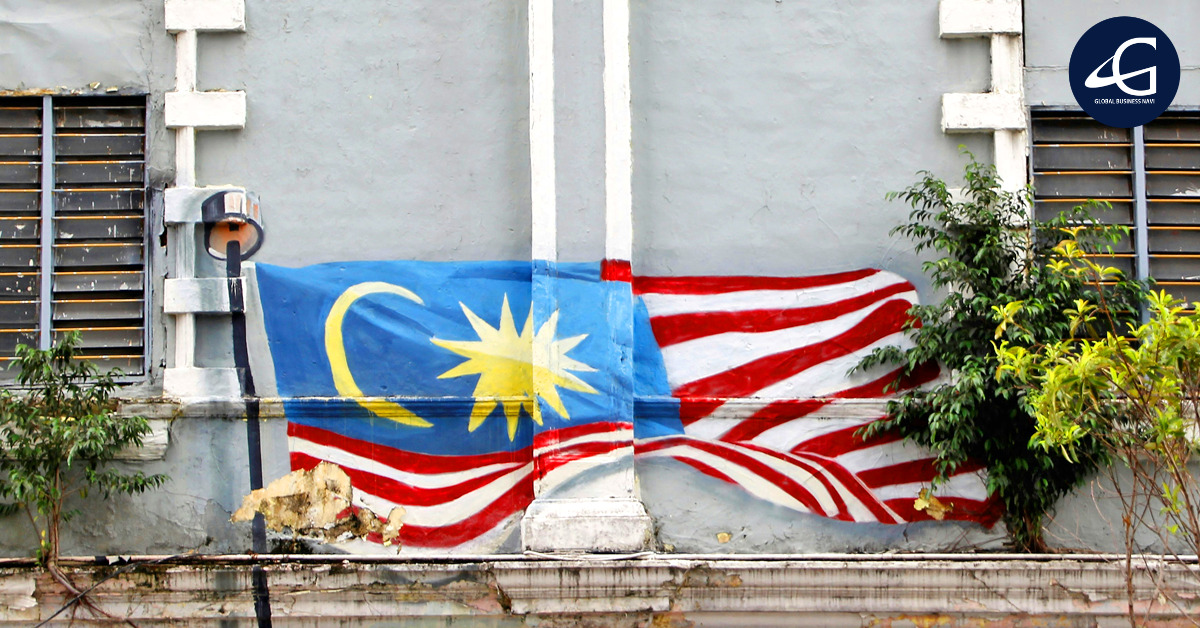
マレーシアは1957年8月31日、イギリスからの独立を果たしました。今年で独立68周年を迎えました。当時は「マラヤ連邦」として出発し、その後1963年にシンガポール、サラワク、サバを加えて「マレーシア」となりました(シンガポールは1965年に分離独立)。現在、8月31日の「Hari Merdeka(独立記念日)」は国家最大の祝祭日であり、国民的行事として位置づけられています。
(引用元: Planning to attend the National Day 2025 parade in Putrajaya? Here’s what you should know | Malay Mail
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2025/08/20/planning-to-attend-the-national-day-2025-parade-in-putrajaya-heres-what-you-should-know/188200#google_vignette)
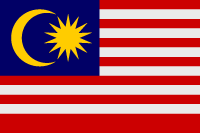
マレーシアの独立記念日に見る祝賀の変容
著者:マレーシアgramフェロー Malay Dragon
公開日:2025年 9月29日
国旗「Jalur Gemilang」の意義

マレーシアの国旗は、14本の赤と白の縞に青地の枠、黄色の三日月と14角星が描かれています。赤は勇気、白は純潔、青は統一、黄色は王権を表し、星は連邦を構成する13州と1つの連邦直轄領を示しています。
正式名称である「Jalur Gemilang(栄光の縞)」は1997年、マハティール首相(当時)が国民公募の後に定めたものです。日本で「日の丸」という通称が広く用いられるように、マレーシア人にとって「Jalur Gemilang」は単なる旗以上に、国民的誇りの象徴として日常的に使われています。
独立宣言と「Merdeka」の叫び
1957年の独立宣言式典において、初代首相トゥンク・アブドゥル・ラーマンが「Merdeka(独立だ)!」を7回唱和したことは有名です。この7回は歴史的シンボルとなり、現在でも独立記念日の公式式典で再現される伝統となっています。マレーシアの小学校では必ず学習する内容であり、国民的記憶として共有されています。
祝賀スタイルの変化
私は15年マレーシアに住んでいますが、過去15年で顕著な変化は、祝賀の”可視性”の高まりです。クアラルンプール市内ではオフィスビルやショッピングモールだけでなく、タクシーやバイクにも国旗が掲げられ、街全体が赤・白・青・黄の色彩に染まります。
以前は政府主導の式典中心という印象が強かったものの、近年は一般市民の自主的な参加が増加しつつあります。特に若者層はSNSで「Merdeka!」と投稿し、国旗や伝統衣装と共に写真を共有する文化が定着しています。
国家理念「Rukun Negara」とナショナル・アイデンティティ
1969年の民族暴動を契機に1970年に制定された国家理念「Rukun Negara(国是五条)」は、多民族国家としての統合を意図したものです。この理念の存在は、独立記念日の祝賀にも影響を与えています。すなわち、国旗掲揚や国歌斉唱を通じて民族間の違いを越えた統一を確認する行為として、祝賀が機能しているのです。
特にビジネスの場においても、企業が社屋や店舗に国旗を掲げ、社員が一体感を持つ光景は日常的に見られます。
経済活動との接点
独立記念日には国内消費の押し上げ効果も確認されています。大手ショッピングモールやEコマースサイトでは「Merdeka Sale」と銘打った大規模セールが実施され、旅行・宿泊業界も国内移動の需要増を見込んでキャンペーンを展開します。
観光省によれば、祝日期間中は国内観光需要が通常期より10〜15%増加するとされ、独立記念日は経済的にも重要な節目といえます。
日本との比較
このように、マレーシアでは国家の象徴が社会生活や経済活動の中に積極的に組み込まれています。国旗を掲げることは自然な行為であり、国家行事を祝うことが個人のアイデンティティ表現につながっています。
一方、日本においては「建国記念の日」が存在するものの、国旗掲揚や祝賀行事は限定的であり、国民生活の中で可視化される機会は少なくなっています。歴史的背景の違いを踏まえる必要はあるものの、両国の比較は、ナショナル・アイデンティティと経済・社会活動との関係性を考える上で示唆に富んでいます。