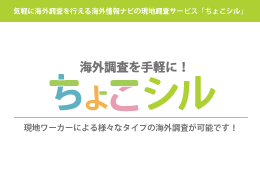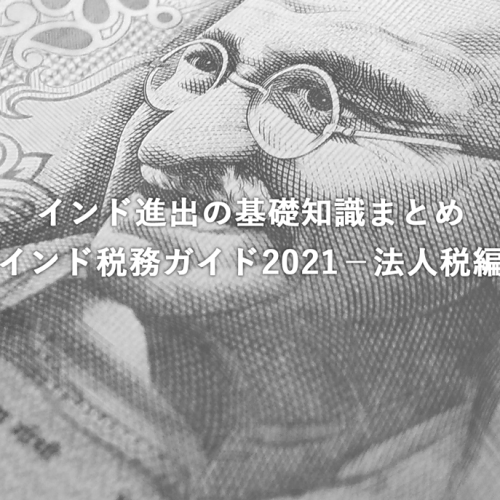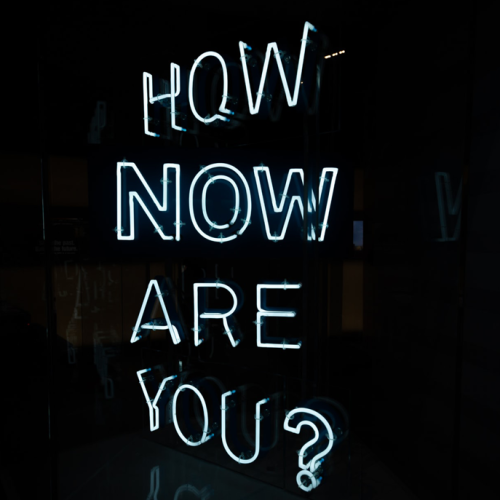海外の投資対象企業のデューデリジェンスとは(2)事例:東南アジア不動産サービス企業の場合

デューデリジェンスとは、日本の機関投資家や事業会社が海外の特定の企業を投資対象として選定した後、そこへの現実的な投資を検討していく際に、その企業が本当に投資に値するのか、現在ないし将来にわたる企業価値が本当に投資金額に見合ったものであるのかどうかを検証するために行う、第一に様々な項目の調査、第二に企業価値の算出作業を言う。
デューデリジェンスについて事例を交えながら3回に分けてお届けしていく。2回目となる今回は、東南アジア不動産サービス企業の場合を考察する。
海外企業のデューデリジェンス事例(2):東南アジア不動産サービス企業の場合
著者:gramマネージャー 今泉 大輔
公開日:2021年5月15日
日本にいるとよくわからない海外の経済事情
日本で生活していると、日本の経済の仕組みや商慣行が当たり前だと思って毎日生活している。しかし海外では、日本の発想では考えられない経済の仕組みが回っており、それが前提となっているサービスも、最初はよく理解できないものだったりする。
東南アジアのある国では、国民の9割が持ち家に居住している。これは社会主義国の水準である。つまりこの国では計画経済的なメカニズムが回っている。従って、日本の企業人の理解では追いつかない経済現象があり、種々の事業が成立している。
持ち家比率が9割ということは、第一に持ち家の前提となる国民の所得水準が高くて安定していることを意味する。日本では昭和の高度成長期の後で「一億総中流」と言われた時期もあったが、現在では大きく異なっている。国民の所得水準が高くて安定しているとは言えない。
この国では、統計を調べて見ると、世帯所得が日本円で年間1,000万円を超える世帯が約40%ある。年金制度が充実しており、年金として積み立てられている資産を合計すると、一定数の世帯は金融資産が1億円に近い水準になる。「国際的な富裕層の基準」は金融資産1億円以上であるから、この国では準富裕層と呼べる層が分厚く存在していることがわかる。
日本は富裕層が極めて多い国であり、約132万世帯存在している。総世帯数が約5,700万世帯であるから、比率は2.3%。これに対して、この国では種々の数値等から10%程度は存在しているようだ。金融資産5,000万円以上1億円未満の準富裕層まで含めると、20%程度は存在しているようである。従って、社会を構成する人たちの2割程度は、準富裕層的ないし富裕層的なライフスタイルを送っている。そこが、日本にいるとよくわからない。
対象国の消費行動を理解するには?
日本はアジアの中では経済先進国であり、なるほどGDPでは今でも世界第3位である。しかし、国民1人当たりのGDPで見ると20〜25位圏。香港、イスラエル、ニュージランドより下である。イスラエルの商都テルアビブに10日ほど滞在したことがあるが、旅行者として感じる物価水準は東京都心と同じだった。
この東南アジアの対象国にも旅行者として、また出張者として滞在したことが何度かあるが、感じる物価水準は東京都心よりもはるかに高い。何か買う度に財布に手応えがある。
日本にいると、こうした「富裕になっている国」の生活感覚や消費行動がよくわからない。それを理解するのに一番いいのは、その国に行って、自炊ができるキッチン付きのアパート(日本で言うマンション)を借りて、地元のスーパーで食材を買いながら、何度も食事をして見ることだ。すると、スーパーで購入する一品目、一品目から、その国の物価水準がリアルに伝わってくる。「ああ、この国ではこの食品がこんなに高いんだな」と。こういう高い食品を国民が普通に食べているのだな、と。すると国民の所得水準は相応に日本より高いんだな、と。
それができない場合は、数字で理解するしかない。世帯当たり収入の水準。国民一人当たりGDPも、名目ではなく、物価水準を勘案した購買力平価で日本と比べる必要がある。所得水準が高いと何が変わるのかを、自分の想像力を膨らませて理解する必要がある。健康にかけるお金。教育にかけるお金。老後の過ごし方。すべてが変わってくる。日本にいてはなかなか理解できない消費行動がある。それを数字によって理解しなければならない。
関係する数字を拾い、パズルのように組み合わせていく
以前、あるクライアントからの依頼により、この国の不動産関連のサービスをしている企業の調査をした際に、日本にいてはよく理解できない商売をやっており、その商売が持続可能なものであるのか、成長性があるのか、最終的には投資に見合う経済合理性があるのか、が解明の焦点となった。
これらを理解するのに、その国の世帯所得の動向、持ち家比率が高いことの背景、政府の住宅政策、高所得を維持するための政治経済、住宅購入に不可欠なファイナンスの仕組み、準富裕層的な住宅購入スタイル、それに伴う家具や内装の消費行動などを、1つひとつ解きほぐして行った。
前提となる知識が何もない国でも、関係する数字を一つひとつ拾い、その意味を分析し、ジグソーパズルのようにいくつものピースを組み合わせていくと、ある時、一人ひとりの消費者の行動が鮮明に浮かび上がり、その思いや意味がよく理解できるようになる。このような理由があるから、このサービスを使うのだと、理解できてくる。そうして、ここがもっとも重要だが、そのサービスの価格が高いのか安いのかが、よくわかってくる。利益が出る水準の価格がいくらぐらいなのかわかる。単位売上当たりでどの程度の営業利益が出るのかがわかってくる。
海外デューデリジェンス:消費行動の背景や心理を把握することが不可欠
海外の投資対象企業にデューデリジェンスをかける時、その企業の財務諸表を見ているだけでは、ほとんどのことはわからない。顧客がその商品・サービスを買うのはなぜなのか。その商品・サービスにはどのような価値があるのか。それを使うとどのようにうれしいのか。何が便利になるのか。
例えば、スマートフォンが全く存在しない国から来た人に、スマホの価値を説明するには、ものすごくたくさんのことを伝えなければならない。定性的な事柄だけでなく、定量的な事実もたくさん示して、これこれこうだからスマホは全ての人に使われているんだよ、とわかってもらわなけれいけない。
それと同じことが、海外の企業のデューデリジェンスにも言える。企業の価値は将来のフリーキャッシュフロー(FCF)の累計の現在価値であり、FCFの大元は顧客の消費行動であるから、その消費行動の背景なり心理なりを定性的、定量的に把握することが不可欠だ。調べるべき事柄は膨大になる。
何もわからない状況から始めるアプローチ
調査会社の一調査担当者としてお伝えしておきたいのは、「未知の事柄を調べる時に、最初は何もわからない」ということだ。対象分野を定常的に追いかけている専門家であれば、常時最新情報を仕入れて認識をリフレッシュできる。対象分野で起こる出来事を一から十まで知っており、その背景も動向も人に説明できる。これからどうなるかを示すこともできる。
けれども世の中には数千数万の対象領域があり、それらをすべてカバーできる調査担当者はいない。その分野の専門家とタッグを組むことができる時はよいとして、そうではない時、どうするのか。
ジャーナリストの立花隆が活躍していた当時に書いた書籍「『知』のソフトウェア」に、そうした何もわからない状況から始めるアプローチが書いてある。一にも二にもひたすら情報をインプットしていく。膨大な量の数字、事実、動向、現象、見解などをインプットして行って、頭の中に「認識の地図」を作る(川喜田二郎のKJ法に近い)。そうすると、その「認識の地図」が意味のまとまりを理解させてくれるようになり、その意味のまとまりを一つひとつ丁寧に見ていくと、驚くべき真実が浮かび上がってくる。
海外の投資対象企業にデューデリジェンスとは(1)事例:電力事業会社(架空)の場合