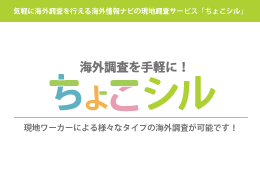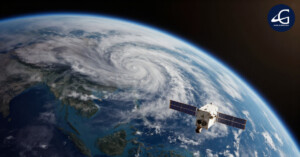なぜ今マレーシアが人気なのか?

今年の大阪万博では、マレーシア館の前に長蛇の列ができていました。テレビやSNSで大きく取り上げられたのが「ロティチャナイ」。鉄板の上で生地を豪快に伸ばしてカリッと焼き上げたそれを、香り高いカレーに浸して食べるマレーシアフードです。初めて出会った人々が「こんな食べ物があるのか!」と驚きの表情を浮かべるシーンは象徴的でした。日本から遠いようで近いこの国――マレーシアが、なぜ今注目を集めているのか。その答えのひとつ「食」について紹介します。
(引用元:Newswav Malaysia’s #1 Content Aggregator :Sekitar Hari Kedua Minggu Kementerian Digital di Pavilion Malaysia, Ekspo 2025 Osaka
https://newswav.com/video/sekitar-hari-kedua-minggu-kementerian-digital-di-pavilion-malaysia-ekspo-20-V2508_1gv7Ka/)
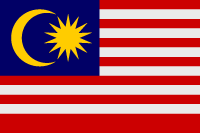
なぜ今マレーシアが人気なのか?
著者:マレーシアgramフェロー Malay Dragon
公開日:2025年11月12日
多民族社会が生んだ豊かな食文化

マレーシアはマレー系、中華系、インド系が共存する多民族社会です。日常生活の中で、それぞれの料理が溶け合うように並び立っている光景は圧巻です。例えば、朝はココナッツミルク香るナシレマ、昼には福建麺、夜はインド風のバナナリーフカレー。旅人はわずか数日でも「アジアの縮図」を舌で体験できます。
私自身も初めてペナンを訪れたとき、地元の人に案内されながら点心を味わい、その後にサテーを頬張りました。異なる文化の料理が、無理なく日常のテーブルに並ぶことに大きな驚きを覚えたのを今も鮮明に覚えています。
屋台文化の力強さ
さらに注目すべきは、屋台文化の存在。クアラルンプールのジャランアロー、ペナンのガーニードライブ、ナイトマーケット――どこも夕暮れ時から熱気を帯び、老若男女が集う社交の場となります。わずか数百円で一皿が楽しめる気軽さも手伝い、観光客にとっては「食の冒険」を楽しむ絶好の舞台なのです。
日本ではフードフェスや屋台イベントは特別な行事だが、マレーシアではそれが日常です。旅行者はこの「日常の非日常感」に強く惹きつけられるのでしょう。
日本食との絶妙な距離感
意外に思われるかもしれませんが、マレーシアでは寿司やラーメン、抹茶スイーツなど日本食がすでに定着しています。クアラルンプールなどの都市部では日本食材店も珍しくなく、和食レストランも数多くあります。そのため日本人にとって、マレーシア料理は”未知すぎない”距離感で受け入れやすいのでしょう。
例えば、ナシレマというココナッツライスをベースにした料理は、小魚や卵、サンバルソースが添えられた「おにぎり弁当」といった感じです。異文化ながらどこか懐かしさを感じさせる、これが日本人の心をつかむ大きな理由でしょう。
SNS時代に映える料理
もうひとつ、近年ならではの要素として「映え」があります。バタフライピーの青い飲み物、カラフルな伝統菓子クエ。こうした料理はSNSで拡散されやすく、食べてみたい!という衝動を直接旅行動機に変えています。大阪万博でのロティチャナイ人気も、その延長線上にあるといえるでしょう。
食は文化体験そのもの
そして何より、マレーシアの食の魅力は単なる味覚にとどまらないことです。手でちぎって食べるロティチャナイ、バナナリーフに豪快に盛られるカレー。こうした身体を通じて文化を感じる体験そのものが、旅の記憶を強烈に刻み込むのでしょう。
私が以前、現地の家庭でナシレマを一緒に包ませてもらったとき、単なる料理以上に『暮らしの一部を共有している』という感覚が生まれました。こうした経験こそが旅行者を再びこの国へと引き寄せる力となるでしょう。
多文化が交差するマレーシアの食
なぜ今マレーシアが人気なのか。その答えのひとつは「食」にあります。多民族が織り成す文化の交差点、屋台に象徴される庶民文化の力強さ、日本人にとっての親しみやすさ、そしてSNS時代が後押しする魅力。これらが合わさって、マレーシアは「おいしい国」として確かな存在感を放っています。
大阪万博での一皿は、単なる話題ではなく、マレーシアという国の奥深さへと誘う入口にすぎないのだと強く感じています。