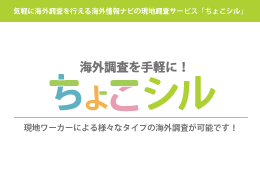シンガポールで昆虫食が許可

シンガポール食品庁(SFA)が、16種の食用昆虫の国内での販売と消費を承認したというニュースがCNNで流れました。今回シンガポール食品庁が承認した昆虫には、イナゴやバッタなど、日本でも食されているカブト虫も含まれています。
豊かな食文化を持っていて、国民食である「チキンライス」は日本人にも多くのファンがいます。そんな食文化豊かなシンガポールの昆虫食の許可には、どのような背景があるのでしょうか?
今回は、その辺の事情を深掘りしようと思います。
シンガポールで昆虫食が許可
著者:シンガポールgramフェロー Malay Dragon
公開日:2025年 3月18日
16種類の昆虫が許可

今回シンガポール食品庁が食用、または動物飼料として輸入を認めたのは、バッタやコオロギなどの直翅類(ちょくしるい、)カブト虫類などの鞘翅目(しょうしもく)ほか、4種目16種類の昆虫です。
昆虫を食用、または動物飼料として輸入する事業者については同庁への登録が必要となり、さらにこれを輸入する海外の加工施設の登録も義務付けられます。さらにその加工施設が、食品安全マネジメントシステム(FSMS)、またはHACCPに基づいて、昆虫の加工を行っていることを証明する書類の提出が求められています。
食用実績のある昆虫が中心
シンガポール食品庁が許可したのは、世界で直接、あるいは加工して食されている実績のある昆虫に限られています。これまでは動物飼料としての昆虫は条件付きで認められていましたが、ヒトの食用の昆虫が認められるのは初めてです。
アジアの近隣諸国では、タイではバッタやスズメバチの幼虫を食べる文化もあり、日本でも古くからイナゴなどは佃煮にして食されてきました。
許可の背景と理由
今回食品庁が昆虫食の許可に踏み切ったのには以下の理由が考えられます。
1. 食料安全保障の強化
シンガポールの食料は輸入に大きく依存しており、実に90%を輸入に頼っています。地元で生産される食料源の多様化を図るために、昆虫食を導入しました。これにより輸入への依存を減らし、将来の食料供給の安定性を高める狙いがあります。
2. 持続可能な食料源
昆虫は家畜と比較して、飼料や水の消費が少なく、飼育の際に温室効果ガスの排出量も低いとされています。また、昆虫は食物連鎖の一部としてリサイクル可能な資源を利用することができ、循環経済の実現に寄与します。
3. 栄養価の高さ
昆虫は高タンパクでビタミン、ミネラル、必須脂肪酸も豊富に含まれています。昆虫は栄養補助食品としても世界で注目されており、特に発展途上国においては栄養改善策として利用が進んでいます
「30 by 30計画」
食料安全保障の観点から、シンガポールでは「30 by 30計画」を掲げ、2030年までに自給率を30%まで上げることを目標としています。
シンガポール食品庁は、食品の自給率に対する取り組みを行う企業に対しては助成金を支給すると発表しています。
食料安全保障を強化
シンガポールは限られた国土と資源しかもたない都市国家であるため、食料安全保障を強化するためにさまざまな取り組みを行っています。
上記の「30 by 30計画」のほかにも、限られた土地を有効活用するために、垂直農業が盛んに行われ始めており、これにより、伝統的な農業よりも少ない面積で大量の食料を生産できる可能性が広がっています。
また、輸入依存が極めて高いため、輸入元を多様化し、食料供給のリスクを分散するための国際的な連携も重視しています。シンガポールは多くの国と自由貿易協定を結び、食料供給の安定化を図っています。国内外の農業技術や食料生産企業との協力を強化し、持続可能な食料供給チェーンを構築しています。