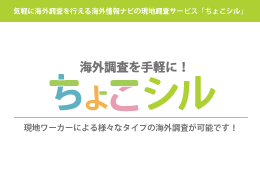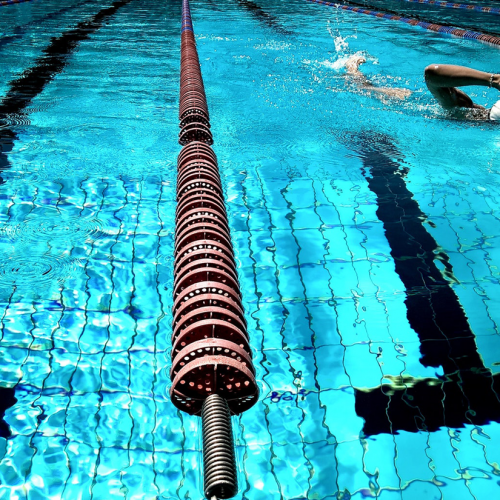中国で浸透する低アルコール飲料市場|日本酒が存在感を発揮できるか

中国の酒の歴史は古く、広大な中国の土地で地域の特色に合った味わい豊かな酒が多く生まれている。昔から酒造りが盛んでよく酒を飲む習慣のある中国だが、現代の若者のアルコールに対する価値観は変化している。中国で浸透している低アルコール飲料と、日本が誇る「日本酒」に対する中国での反応から見る中国の酒市場を解説する。
中国で浸透する低アルコール飲料市場|日本酒が存在感を発揮できるか
著者:上海gramフェロー 米久 熊代
公開日:2024年6月16日
- 中国で推し活が人気 日本のIP商品の消費額が増加
- 必ず知っておきたい中国トレンド「新中式」とは
- 中国で流行している貧乏セットとは 新しい形の貧乏セットが話題に?
- 深圳日本人男児殺害事件 警戒体制続く在中日本人
昔から親しまれている白酒に対する変化

中国の酒といえば「白酒」を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。ブランデー、ウィスキーと並ぶ世界三大蒸留酒のひとつだ。中国の貴州省で造られている「茅台酒(マオタイ)」は中国を代表する高級白酒である。53%という高いアルコール度数でも、不思議と二日酔いしないことでも知られており、中国全土で親しまれている。会食や接待では度数の高い白酒を小さいグラスに注ぎ、一気に飲み干す。これを一杯ごとに何度も乾杯して繰り返すため、酒に慣れていない人は簡単に泥酔してしまう。メンツを非常に大事にする中国人にとって、高い酒をたくさん振舞うことはメンツを立てることができ、昔からの中国流のおもてなしスタイルなのだ。
しかし、最近の中国人の若者は白酒離れが進み低アルコール飲料を好む傾向に変化してきた。こうした世間の動きに合わせ、高級白酒ブランドの茅台メーカーは。茅台酒を使用したアイスや中国のコーヒーチェーン店「瑞幸珈琲(ラッキンコーヒー)」とコラボしたラテを販売するなどして大ヒット。SNSで度々話題となり、何とか白酒離れを防ごうとした。
中国の若者が牽引する低アルコール飲料市場

昨今の中国の若者は、コロナ禍の影響による宅飲みの増加や健康ブームの高まりを背景に、大酒を飲むよりも酒を嗜む程度の「ほろ酔い」ぐらいがちょうど良いという価値観に変化してきているという。
中国ではアルコール度数20%以下を指す低アルコール酒市場が年々成長し続け、2023年には6,300億元(約12兆円)を超えるという。こうした低アルコール酒市場の急拡大を牽引するのが、中国の若年層だ。
日本では若い世代ほど飲酒習慣が少ない傾向にあるようだが、中国では京東(JDドットコム)の販売実績データによると、酒類購入者の若年化傾向が顕著になっている。「90後」(1990年〜1994年生まれ)、「95後」(1995年〜1999年生まれ)、「00後」(2000年以降生まれ)世代が酒類の主力消費層となりつつある。また女性が低アルコール酒消費の6割超という調査結果もある。
(引用元:ジェトロ(PDF)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/agriportal/platform/cn/pf_pcc.pdf)
中国の若年層の女性が多く利用しているSNS小紅本で、「酒」「ほろ酔い」と検索をすると、様々な缶チューハイやリキュール類を投稿している人が多かった。購入しやすい価格で飲みやすいことが人気の理由にある。ジュースなどとブレンドして自分好みのオリジナルドリンクを作ることができるため、低アルコール飲料を使用したアルコールドリンクのレシピ投稿は反響がある。

低アルコール飲料を飲むのは女性が多いイメージだが、最近では男性にも人気が広まっている。中国で低アルコール飲料を広めた飲料大手の「RIO」が、男性向け低アルコール飲料を販売するなどして開拓し、若い男性にも浸透しつつある。
また、中国では甘口で飲みやすい梅酒などの果実酒や「日本酒」が低アルコール飲料として好評だという。
中国での日本酒に対する反応

中国では、アニメやドラマの影響から日本の飲食文化が認知され、筆者が住む上海市では至る所に日本料理屋が立ち並び年々数を増やしている。日本食を好む中国人は多く、日本を代表する「酒」を料理の一部として飲む人が昔より増えているように感じる。
昨今の健康志向ブームでは、糖質0・脂質0といったヘルシーで健康的な食べ物や飲み物が好まれているため、水と麹、米で造られている日本酒は、まさに現在の消費トレンドに当てはまっていると言えるだろう。
日本の財務省が発表した貿易統計によると、2023年の日本の中国向け日本酒輸出は、数量で前年比21.6%減の5,794キロリットル、金額で同12.0%減の124億7,000万円となった。2022年までは、新型コロナウイルス禍の影響が出た2020年を除いて増加を続けてきたが、2023年の減速は東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水問題や中国の景気減速による消費低迷などの要因が大きいとみられる。中国向けの日本酒輸出は減速しながらも、2023年の国・地域別では依然として1位(金額ベース)を保っており、2位の米国(90億9,000万円)、3位の香港(60億2,000万円)を大きく引き離している(表参照)。中国向け輸出額が全体に占める割合は30.4%と、前年比0.6ポイント増えており、日本酒の輸出市場に占める中国のプレゼンスは高い状況が続いている。
(引用元:ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2024/9e352a73c89a83ae.html)
2020年の新型コロナウィルスと2023年の処理水問題や中国の景気減速の影響を除けば、日本酒の輸出量は増加傾向で、中国において日本酒は需要のあるアルコール飲料だということが分かる。
日本料理屋に日本酒があることはもちろんだが、居酒屋や高級中華料理屋などでも日本酒を取り扱っている店が増えている。また、中国の飲食店では酒の持ち込みができるため、ECや高級スーパーで日本酒を購入して店に持ち込む消費者も居ることから、日本酒は中国人の間で着実に親しまれてきているように見受けられる。
まとめ

今後の中国では、クオリティが高く安価な中国産の日本酒や、模造品の出回りなどが懸念され、2024年も処理水問題や低調な個人消費の影響は続くと見られる。その一方で、中国は日本酒の最大の輸出市場であり、低アルコール飲料と健康志向ブームとなっている現在、開拓余地があるため今後の発展が期待できる市場だ。中国よりも一足先に低アルコール飲料やノンアルコール飲料が浸透した日本の先進的な例をヒントに、中国でビジネスチャンスを掴むことができるかもしれない。